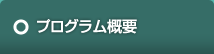- 南山大学ホーム
- 日本語トップ
- 多文化社会における英語による発信力育成
- プログラム概要
- これまでの取組
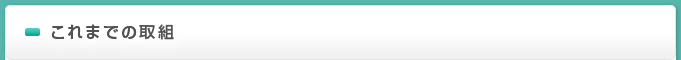
本取組の特徴は、学生の企画・運営委員会が中心となって、国際ワークショップ、国際シンポジウム、特別講演会、卒業論文中間発表会等の行事を企画・運営する点にありますが、平成21年度は取組初年度ということもあり、学生の企画・運営委員会を組織した上で、教員が骨組みを作った行事に学生が参加し、企画・運営の体験を行うインターンシップ的な活動が主な活動となりました。実質的に事業が開始したのは2009年11月でしたが、約5ヶ月の間に、国際ワークショップを2回、特別講演会を2回行い、加えて学生の運営委員会が中心となって卒業論文中間発表会も行いました。学生の運営委員会のミーティングも初回からすべて英語で行われ、「英語による発信力育成」を目指す本取組にとって、非常に希望が持てる初年度であったと言えます。
2009年11月4日(水)
卒業論文中間発表会は、従来ゼミ単位で行われてきましたが、2008年度に初めて学科行事として位置づけました。今年度は、学生の企画・運営委員会が主体となって行う本取組の主要な行事のひとつとして、2009年11月4日(水)に5つの教室に分かれて卒業論文の中間発表を行いました。司会、進行、発表、質疑応答のすべてが英語で行われ、発表者はパワーポイントによるプレゼンテーションによって自分の専門分野についての発表を行いました。
[ 詳細はこちら ]
2009年11月20日(金)
第1回国際ワークショップは、2009年 11月20日(金)に Erin Chung ジョンズ・ホプキンス大学准教授、石田訓夫本学客員教授、David Mayer 本学名誉教授をパネリストに招き、「移民問題を日米比較から考える」をテーマに、すべて英語でワークショップを行いました。日系ブラジル人、中国人留学生、日本人の3名が学生代表質問者として登場し、それぞれのパネリストに対して英語による質問を行い、活発な質疑応答をリードしました。
[ 詳細はこちら ]
2009年12月15日(火)
第2回国際ワークショップは、2009年12月15日(火)に Jonas D. Stewart 名古屋アメリカンセンター館長を招き、"Meet an American Diplomat"と題し、2009年にアメリカ合衆国と日本の両国で起きた政治上のCHANGEについて、日米関係の歴史的背景も把握しながら理解を深めました。アメリカ政治研究およびアメリカ外交研究を専門とする学生を中心に、すべて英語による質疑応答が行われ、取組2年目に続く良いワークショップのサンプル提示を行うことができました。
[ 詳細はこちら ]
2010年1月18日(月)
第1回特別講演会は、2010年1月18日(月)に 、Christopher D. Tancredi 慶応義塾大学言語文化研究所准教授を招き、"Condition B as an Epiphenomenon" と題した言語学の講演会を開催しました。普遍文法の研究を続けるTancredi 氏は、生成文法理論の最新理論を踏まえた分析を提示され、学生の知的好奇心を大いにかき立てました。
[ 詳細はこちら ]
2010年2月22日(月)
第2回特別講演会は、2010年2月22日(月)に Bonnie D. Schwartz ハワイ大学教授および Kamil Ud Deen ハワイ大学准教授を招き、それぞれ "Let’s Go on a Hawaiian Tour (of Child L2 Acquisition)"、 "Binding in Thai: The Case for Nativism" と題した言語獲得に関する講演を行った他、学生の理解を助けるために、有元將剛、村杉恵子本学教授が各講演の前に解説を行いました。この講演会で特筆すべきは、最初に学生代表が本取組についての概要説明を英語で行ったことで、学生の英語による発信という意味から、大いなる一歩を踏み出すことができたと言えるでしょう。
[ 詳細はこちら ]