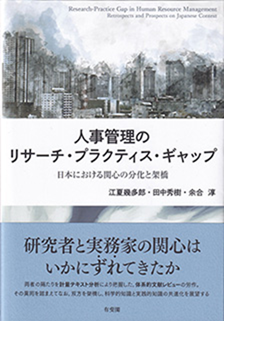教員コラム 経営学専攻
研究の立場,実務の立場(経営学 余合 淳 准教授)
2025年07月01日
この数年は『「人事管理における研究と実務」に関する研究』に携わることになり,昨年その成果を著書として出版した(江夏幾多郎・田中秀樹・余合淳『人事管理のリサーチ・プラクティス・ギャップ―日本における関心の分化と架橋―』有斐閣,2024年)。詳細な内容についてはぜひ著書を手に取って頂きたいが,この研究は,研究と実務の関係を改めて考える良い機会となった。
この研究の中では,1970年代以降の学術文献や,実務家の読む専門雑誌の書誌情報を解析している。研究者が何に関心を持ち,実務家が何を大事にしているかがよくわかる一方,両者の「埋まらない溝」も感じさせる。研究結果からは,研究者には「もっと現場観察とスピード感を」,実務家には「もっと長期的視点と科学的な厳密さを」等とアドバイスもできるのだが,そもそも「観察者」と「行為者」の役割は異なる。両者の差をゼロにするのではなく,お互いがどうかかわるかが重要であると感じている。
実務家からは「文系の学問は役立たない」という声も耳にする。教育者としての大学教員には実に耳に痛い話だが,この研究をしている中で感じたのがそもそも「学問を実務に使おうとする」人が稀有かもしれないということだ。それは,実務の世界が「今のトレンドは何か」「上司,本社,親会社が何を言うか」「顧客が何を要求するか」といった,利害関係に基づく緊急性のある事項を重視することが多く,「何が正しいか」「何が原因か」「この仕事に意味があるか」等が軽視されやすいことにありそうだ。しかも学問の世界は往々にして「厳密」かつ「複雑で難解」だ。こうした違いが,実務と研究の距離を広げている印象がある。
しかし,例えば,「いつも通りの仕事の手法で行き詰まりを感じている」「意味が分からない仕組みやルールにがんじがらめになっている」「働く気力も魅力も見出せない」ような実務家には,研究の世界は異質だがきっと魅力的でもあるはずだ。論理に厳密で,複雑な分析手法を用いた学術的な知見が「筋は通っているがただの理想論」に見えるかもしれない。しかし,理屈も理想もない仕事を実践するのはきっと相当な困難を伴う。実務家が時には立ち止まって,自分の立場と役割を俯瞰的に眺めてみることは,実務に(そして実は研究にも)良い刺激になるのではないかと感じている。学生時代に学術の魅力に気付かず,今実務にどっぷりな人にも,今後も様々な機会を通じてその魅力を粘り強くお伝えしたいと考えている。