教員コラム 経済学専攻
研究指導は教育か研究か(経済学 岸野 悦朗 教授)
2025年01月31日
早いもので当職が大学院で租税法研究の授業を担当して10年余りが経過した。この間、当職の指導を受け修士論文を作成し、卒業した学生は38人を数える。そして、卒業した学生の大半は、2年間にわたって培った租税法に係る研究実績としての修士論文を当大学の紀要である『南山論集』に投稿し、その成果を披露している。
ところで、修士論文の作成に当たっては、大学院の授業科目である「研究指導」の時間が割り当てられ、教員はその時間を用いて指導することとされている。しかし、学生にとって修士論文の作業は、課題の設定、争点の確立、文献の収集・分析・検討、論文の骨格の策定・肉付け、全体を通じての点検等膨大な作業を伴う研究内容の成果の取りまとめであり、研究指導+α程度の時間で論文を完成させることは不可能である。
とりわけ、論文の論理展開から結論に向けての流れは、租税法の分野においては100%正しい結論がないことから、結論に向けての論理構成が重要となる。そして、各学生は的確な論理を組み立てるためには定量的な作業量でもって終わることはなく、結論を導き出すための思考力、創造力等を発揮したうえで、自己が正解と考える結論としての出口の見えないゴールに向けて作業を行うことになる。
一方、指導教員としては、修士論文の指導に当たって他の講義等の場合とは異なり、学生が選択した個別の研究課題に係る問題点を見極め、論理展開の的確性、引用文献の妥当性、文章表現の正確性等多方面にわたり指導を行うことが要請され、こうした要請にこたえるためにも当該学生以上に各学生の課題に係る考察を行い、当該学生が示す結論、論理展開、検討プロセス等の内容はもちろんのこと、それ以外の視点をも踏まえた上で、各学生の考察内容を点検し、論文として的確らしく示されるようにきめ細くアドバイスする必要がある。そして、指導に当たっては、学生の状況に振り回されることが多く、計画的に実施できる研究や講義に比べてストレスを感じざるを得ない。
ところで、こうした研究指導の内容を踏まえると、修士論文の指導は研究指導との名目で授業の一環としての教育として整理されているが、その実態は各学生の選定した修士論文の課題に係る研究といった要素がかなり色濃く、研究指導は指導教員の研究の一部と捉える見方も可能ではなかろうか。
そして、これまで各指導学生が研究成果として著わした『南山論集』の著作者は学生ではあるが、毎年、『南山論集』が刊行される際には、その成果の一部については指導教員としての隠れた研究成果であると自己満足に陥り、指導に係るストレスを解消するのである。
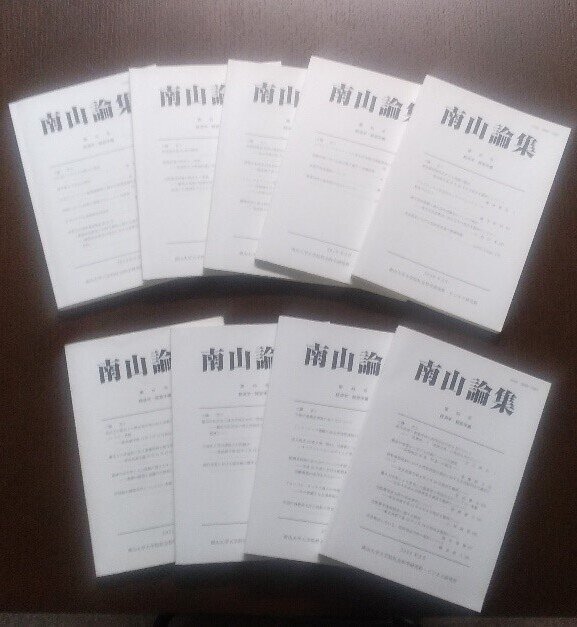
これまでに当職が指導を行った学生の修士論文が掲載された「南山論集」